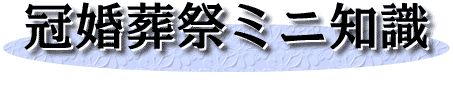
| 弔辞 |
| 弔辞を頼まれたら断らないで引き受けるのが礼儀です。弔辞は喪主に保管されますので、丁寧に書きましょう。文章は真心が伝わるように自分の言葉で書くのが良いでしょう。 ◆ごく一般的な弔辞文作成のポイント◆ 1.まず亡くなったことへの悲しみを述べます。 2.次に故人の業績や人柄を、あまり大げさにならない程度に讃えます。 3.そして、遺族を励まし、自分にできることがあれば力になりたいと誓います。 4.最後に故人の冥福を祈り結びとします。 |
| 弔電 |
| 葬儀に出席できない場合、電話でのお悔やみは避けるようにしましょう。喪家では葬儀の準備などで忙しく、さまざまな連絡用に電話を使用しなければならないからです。なるべく電報を使うようにしましょう。 ◆弔電の文例◆ ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。 ○○様のご訃報に接し、お悲しみをお察し申し上げますとともに衷心より哀悼の意を表します。 ご逝去をいたみご冥福をお祈り申し上げます。 ご生前の笑顔ばかりが目に浮かびます。どうぞ安らかな旅立ちでありますよう、心からお祈りいたします。 |
| 忌み言葉[禁句] 葬儀の際の挨拶や弔辞にはふさわしくないとされている言葉があります。人によっては気にされる方と気にされない方がいますが、できれば使わないほうが良いでしょう。
|
||||||
| その他のマナーと心遣い 香典のお断りがある場合は、無理に渡すことはひかえましょう。また喪主から精進落としや通夜振る舞い等をすすめられた場合、一口でも箸をつけるのが礼儀ですが、喪主の家族は看病や、さまざまな心労で疲れていることも考えられるので、なるべく早めに切り上げるようにしたいものです。 |
||||||
